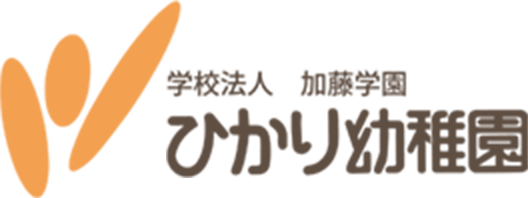前掲書では、歴史的に多くの指導的立場の人々が、上の考えを信じていたことの証拠を挙げています。ざっとあげますと、
- 中世に描かれた絵≪幼いイエスに木製の歩行器を送るヨセフ≫
- 1577年フェラリアスの記録
- 1646年のレンブラントの絵
- 1700年ウイリアム・カドガン医師のすすめ
- 1906年広告
- 2013年シアーズ社のネット広告
などです。(同書84~85ページ)
20世紀~21世紀の研究によると、歩行器を使っても子どもは早く歩けるようにはならず、むしろ「歩こうとする欲求を損なうものである」と結論づけています。「乳児のほとんどは特別な訓練なしで歩けるようになります」(同書86~87ページ) 乳幼児の自然な生理的成長欲求にまかせて最低限必要な安全確保さえしていれば歩けるようになる、ということでしょう。私も二人の子どもがそれぞれ1才になるころ、子ども用のいす・ソファー代わりに歩行器に一時的にすわらせたこともありましたが、それぞれ順調に歩き方をみずから体得していきました。また、「はいはい」歩きも大いにさせた方がその後の全身の発達に良い、と言われますが、これも個人差があり、私の長男は大いにはいはい歩きをしましたし、ちょっと歩けるようになると、外へ自分で戸・網戸を開けて出て行ってしまうので、網戸の上部に針金で手製の鍵をつけたくらいでした。また長女は、はいはい歩きはほとんどしませんでしたが1才の頃は毎日歩ける歩数・距離がぐんぐん伸びていくのが目に見えてわかるくらい発達していきました。
著者は、別の視点から歩行器に安易に頼ることの危険さも指摘しています。歩行器に座らせておくとちょっと子どもから目を離したすきに知らない間にどこかに行ってしまうなどの心配がない、と安心してしまうことから、歩行器使用中についつい目を離して「階段から落ちる、テーブルやストーブから熱いものを落としてやけどを負う、プールや浴槽で溺れる、中毒を起こす物を触ったり口にする、」などの危険がある、と言います。いずれにしても、やはり子どもが歩き始めたら逆に今までなかった危ないことが多く待ち構えているものですから、この時期は、基本的にいつも誰かは見守っている必要はあるのでしょう。