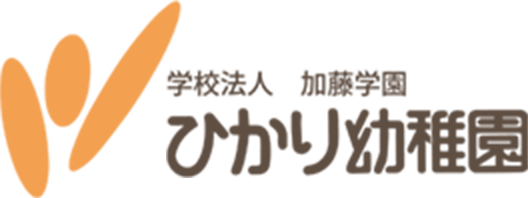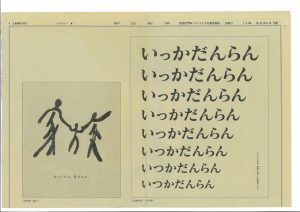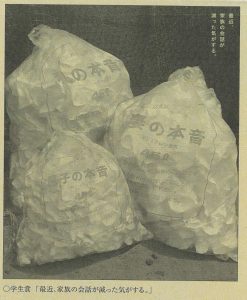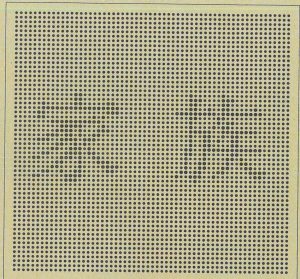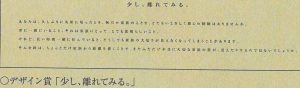赤ちゃん言葉というのは、日本でもアメリカでもその他の国でもよくあることのようです。どんな赤ちゃんも、肌がきれいで身体・手足もとっても小さくて可愛らしいもので思わず触りたくなってしまう魅力がありますよね。そんな赤ちゃん・乳児に話しかけるときは、赤ちゃんに寄り添いたくなる大人の心理から、赤ちゃん言葉が自然に出てしまうものでもあると思います。
しかし、こんな大人の自然な心理に反して、赤ちゃん言葉を子どもの言語発達の妨げになる、と批判する人も少なからずいるようです。
けれども前掲書では、最近の研究から、「乳児は、赤ちゃんが話す言葉を好んで聞くということを明らかにしています。」「乳児が赤ちゃん言葉を聞くと、より注意を払ったり、嬉しそうな顔をしたりすることで、大人の赤ちゃん言葉の使用を強化している可能性があります。つまり、赤ちゃん自身が大人にもっと赤ちゃん言葉を使うように促しているのです。」「赤ちゃん言葉が好まれるのは、嬉しい感情を表現したいからだとする研究もあります。」と述べています。(同書100ページ) 冒頭に述べたように、赤ちゃんに出会った大人の嬉しい感情の現れには、悪い影響はないようです。
私たち幼児教育にたずさわる者は、幼児にお話をするときには、基本的にはその場にいる一番年少児の言語理解能力に合わせて話すように心がけます。これは子どもにまごころを伝えたいときにとる当然・自然の「子どもに寄り添う」姿勢です。けれどもそんな中でも、大人のことばが部分的に出てきますし、そんな話を何度も聞くうちに、自然と大人のことばを少しずつ理解し獲得していきます。「子どもは他の子どもから大人っぽい言葉をたくさん学ぶということです。赤ちゃん言葉をたくさん聞いている幼児でさえも、他の子どもたちから大人っぽい言葉をたくさん吸収しているのです。なぜなら、乳幼児が耳にする言葉の大部分が大人同士の会話だからです。」(同書101ページ)
「親が赤ちゃんに赤ちゃん言葉を使っても明らかに大丈夫です。赤ちゃんとのコミュニケ―ションは人それぞれで、これが正解という方法はありません。一番大切なのは、“赤ちゃんとコミュニケーションすること”です。」「多少変化のあるコミュニケーションスタイルは赤ちゃんにとって一番いいかもしれません。親は子どもに赤ちゃん言葉を使うかどうか、あまり気にする必要はありません。その代わり、赤ちゃんとの楽しいやり取りに集中したほうがいいでしょう。」(同書102ページ)
本欄の最初の方で、乳幼児期の、禁止語・命令語でない温かい・丁寧なことばがけ、子ども自身に考えさせる配慮深いことばがけが、子どもの生涯にわたる成育・成長・活躍に大いに影響・寄与する、という研究成果の話を述べています(『3000万語の格差』ダナ・サスキンド著)が、真意は通ずるものがあると思います。