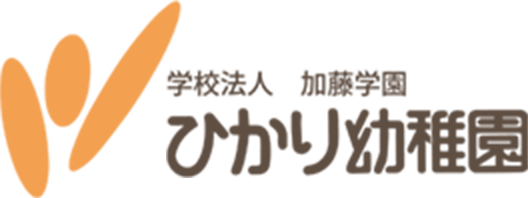前回ご紹介した汐見稔幸氏の著書『ほめない子育て』には、「父親の子育て参画」という話題も述べられています。この問題について今回は考えてみましょう。
氏は、まずは昭和以来の父親の子育て参加事情について、ざっとふりかえっています。第二次世界大戦前の時代は、「家父長制度」の名残りで父親は、家庭(の近く)で仕事に専念して家計を支え、家庭の中ではどっしりと威厳をもって存在し、細かな子育て作業には基本的にかかわらず、ときどき子どもの進路決定などのおおまか・重要な課題にのみ有力な意見を言うだけであったようです。
そして終戦後は、復興期から高度経済成長期にかけて、男親は「企業戦士」としてガンガン働き、家事・子育てにはほとんど時間的にも精神的にもノータッチでよしとされていました。
しかし、昭和の末期ごろ(昭和60年ころ)から増えてきた子どものいじめ・不登校・自死といった社会問題の学術的な調査・分析が進んでいくと、そこには「父親の存在」がないことの気づき・指摘が出てきました。結婚家族内でも母親のみの今で言う「ワンオペ育児」の状態が多く、母親一人が悩み・苦労しながら子育てしている姿が浮き彫りになってきたのです。
そのころから、汐見氏らが先陣を切って、「父親の子育て参画」を訴えて来られました。汐見氏は、多くの著書やテレビ子育て番組や『父子手帳』という本を作成したりして、父親もできる範囲で大いに子育てに参加した方が、子どもは幸せに・健全に育っていくのだ、という教育論を展開していきました。幼少時から子どもは、お母さんはもちろんのこと、お父さんやお祖父さんお祖母さんその他さまざま多様な人格に愛され関りを持った方が、幅広い人格を形成していくのだ、と言うのです。
また汐見氏は、「父性文化と母性文化をバランスよく展開して!」ということをおっしゃいます。「父性文化」とは、木登り・石ころ集めコレクション・「高い高い!」遊びといったダイナミック・ワイルドな刺激・冒険・挑戦を子育てに盛り込んだものであり、これに対し「母性文化」は、転んだり友だちとぶつかったりして痛い思いをしたとき、優しく包み込み共感し安らかに慰めてくれる心性・保育文化のことです。この両者がバランスよく混ざったり交互に繰り返されたりして多様な育児環境・生活が展開されることが乳幼児の成育にはとても大切である、と訴えられます。(前掲書・第4章 お父さんの育児参加・141~176頁)
お父さんお母さんも、夫婦とは言えもともと別人格ですから、考え方・感じ方・好み・興味関心には少なからず違いがあり、子どもへのまなざし・見方も違うし、保育・教育観にも違いがあるものです。その両者が好意的・協力的に話し合いを重ねて、両者の良い所を生かしながら子どもに良い影響を与えていく、というのが望ましい保育・家庭教育なのでしょう。
最後に私なりの意見・知識もつけ加えますと、「ベテランの小学校の先生は、子どもを見たり少しつき合うだけで、その子の家庭(の近く)に祖父母がいるかどうかすぐわかる」という話を聞きました。それほど普段の家庭生活が子どもに与える影響は大きいということなのでしょうね。