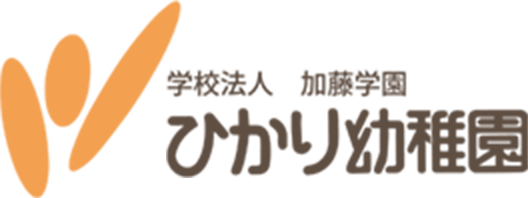本欄の前2回で紹介・解説してきた汐見稔幸著『ほめない子育て』の第3章・第5章では、氏の全体のまとめ・結論的な主張として、これからの国際化(グローバル)社会で自己主張・個性を大切に育み展開していくことの重要さを述べています。
汐見氏は昭和22年生まれで、お母さま・お祖母さまがそれぞれ大正・明治生まれの影響でしょう、明治以来今日までの近代日本の劇的な変動により教育・保育の状況・環境もかなり変容してきてこのことが子どもの育ちに多くの影響を及ぼしてきている、という問題意識が氏の教育論の根底にあります。
前々回の本欄でもそうした教育事情の変化を、4点ほどにまとめて概観しましたが、戦後日本の高度経済成長以前の日本の子育て事情は、氏は「放し飼いの子育て」だったと観ています。今のように買ってきてすぐに食べられるお惣菜を売っているコンビニ・スーパーもないし、今では当たり前のような掃除機・洗濯機・炊飯器・湯沸かし器などの家電もなかった時代には、家事(買い物・料理・掃除・洗濯)・畑仕事・育児・近所づきあいなど、主婦にまかせられる執務で、一日14時間半働いたと言われています。そんな忙しい毎日では、7~8人兄弟姉妹が珍しくないという大勢の子どもと一緒にじっくり過ごす時間などありませんから、大勢の兄弟・近所の友だち同士で遊ばせたり、長子に乳幼児の子守をさせるなど、子どもたちの集団活動・生活・自治的社会が自然に発生し機能していました。
ですから、家庭では家長たるお父さん(またはお祖父さん)が、デーンと威厳をもってかまえていて、地域社会や家庭の道徳・価値観をみなに教育していたことから、子どもたちは少なからず窮屈な思いも持っていましたが、「お母さんやお父さんの前では「よい子」を演じてみせても、地域社会に出たときに自分らしくふるまい、息抜きをすることができたのです。親が知らないところで、隠れ家に隠れて冒険したり、いたずらしたりしながら友だちといっしょに思い切り自己主張することができたわけです。そうやって子どもなりに、うまくバランスをとっていたと考えられます。」(同書136ページ)
今日の「お母さん、お父さんも子どもを小さいうちからある枠にはめ込もうとするのではなく、なるべくのびのびと探索活動ができ、思う存分自己主張ができるような環境を与えてやることが大切なのです。」(同書138ページ)
確かに戦前は、旧憲法のもと、確固たる道徳的価値観が上(国家)から地域社会に強力に降りてくる上意(じょうい)下達(かたつ)社会ではありましたから、日本人の特徴的な性格として、「世間様に申し訳が立つように」生活し子どもを教育しようとする傾向がいまだに強く残っていますが、まったく逆に、ほんの300年くらいしか歴史がなく我が国の歴史はこれから自分たちが作るんだ、という気概からすべてが出発しているアメリカなどでは、「皆と同じように、横並びに」ではなく、皆とは違う自分だけの個性を持ち発揮していくことが最善とされるようです。
大勢の友人・知人や大人たちと交流すれば、人はみな一人として同じ人はなく、性格・好み・考え方・感じ方が大きく違うものである、と知るものです。ここから出発して、「みんなちがって、みんないい」(金子みすず)の境地に達するのがこれからの国際(グローバル)化社会時代を生き生きとたくましく生き抜いていく哲学である、と氏は主張されるようです。