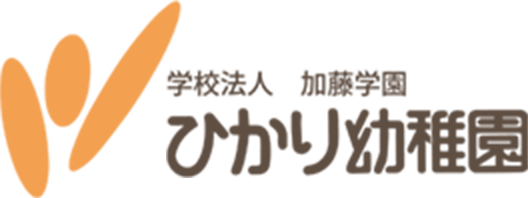横井也有の『健康十訓』の8~10条は、精神面の問題です。
八.少憤(少怒)多笑(いらいら怒らず朗らかに笑いましょう。)
健康への笑いの効用は、多くの医学者・宗教者が提唱しています。笑いはガンを退治するNK細胞を増やすことも医学的に証明されています。
「笑う門には福来る」という諺(ことわざ)もあります。誰しも明るい人の方へ引き寄せられますよね。
九.少言多行(文句ばかり言わずにまずは実行しましょう。)
このことばを見て、「有言実行(ゆうげんじつこう)」(発言・宣言したからには、責任をもって必ず成し遂げること。)を思い出しました。「禁煙」など他者に宣言すると、「言っちゃったからやらなきゃなあ~」という責任が発生するのですが、半面ことば倒れになってしまうリスクもあるので、場合によっては「ことば少なに行いが多い」方がもっといいのでしょう。
十.少欲多施(自身の欲望を控え周りの人々に尽くしましょう。)
本欄の最初のところで、仏教の「無財の七施」について述べました。必ずしも金品のやり取りに頼らなくとも、ことば(語り・手紙・イラストなど)・笑顔・スキンシップなどによる「施し(奉仕・サービス)」ができ、知性も感性も豊かに満たされることができます。
私がこれまでに、心の持ち方(精神(メンタル)面の問題)について、さまざまな啓発書を読んで、整理した文をここで載せましょう。
(1)どんなことが起こっても、失敗を重ねても、常に前向き・上向き志向で明るく大らかに受けとめ、次の一歩を踏み出す。笑い(ユーモア)ある生活を心がける。「笑う門には福来たる」「失敗(の悩み)は誰にでもある」「失敗しない人間なんてない」「七転び八起き」などのよく聞くことばを繰り返して唱えてみるのも良いですよ。
(2)社会的に認められる趣味・仕事・ボランティア等にたずさわり、心身を大いにのびのび働かせ、活性化する喜び・生きがい・やりがい・はりあいを感じる。
(3)家族・友人知人・他者との友好的な関係をもつ。仏教では「友人は選んでよい」とも言っています。
(4)一日終わったら、どんな結果であろうとも感謝の気持ちで締めくくる。
(5)ストレス発散:お風呂などでリラックスして、副交感神経を豊かにする。深呼吸(腹式呼吸・鼻呼吸で)・森林浴・草花樹木の匂いもよい。自分の好きな音楽を聴く・歌う・楽器演奏する、ミニ座禅(一日10分など)もよい。(「動」の後は、「静」)
(6)何歳になっても自分の関心・好奇心にしたがって自分なりのペースで楽しみながら学ぶ。(人から・本から・実践体験から・ネットから)
(7)真の・正しい信条・信仰心をもち、人生の根底・終着地を完全に保証され・支えられている安心感をもつ。
たくさんありますね。全部やらなきゃ!とあせると逆にストレスになります。「自分のやれること・やりたいことを選んで、マイペースで、気持ちよく」をモットーにどうぞ試してください。