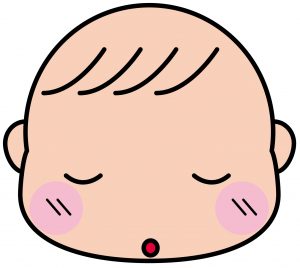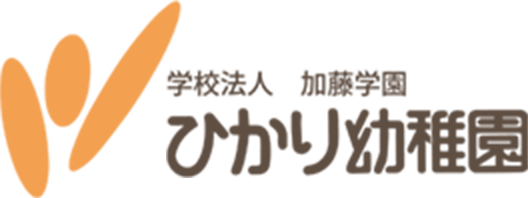前掲書の第2章では、泣くことが唯一の「仕事」である赤ちゃんは、夜、親の望むように寝てはくれないことが子を持つ親のほぼ全員の悩みの種であることから話を始めます。そして今から100年以上前から、泣いて寝てくれない赤ちゃんに対しては、「泣かせておくCry It Out」ことが勧められてきた、と述べています。しかし、現代の親たちは、それがどんなに苦痛・悲しみをともなうことであることかに悩んでいる、と観察・判断しています。そうしたことから、現代では、クライ・イット・アウト法は、赤ちゃんの健全な精神発達には悪い影響がある、というのが定説のようになっているようです。
私も、二人の子どもの子育てに(部分的に)関わる中で、子どもが何で泣いているのか分からなくてとても悲しい思いをしたこともずいぶん経験しました。二人の子どもはいわゆる「夜泣き」はほとんどと言ってもいいくらいありませんでしたので、その点では育てやすかった、と思っています。一般的な話として、アパート住まいなどの若い夫婦・家族では、赤ちゃんの夜泣きがひどいと、隣近所の住民に迷惑がかかるので、夜中に若いお父さんが赤ちゃんを抱っこしてあやしながら外を散歩して、赤ちゃんが泣き止んだら住まいへもどってくる、などということも聞いていましたが、わが家ではその必要・経験はありませんでした。
さて、同書の内容紹介を続けましょう。最近の研究(2010年)では、「クライ・イット・アウト法」が乳幼児の精神的健康や愛着を阻害することはないと報告しています。(同書72ページ)私たちを安心させる2点の見解をもってまとめにしましょう。
①「子どもはとても傷つきやすいのでどんなストレスにも対処できないと思われていますが、実際は、子どもは人生のストレスに対応する能力が十分にあります。」「さらに言えば、ストレスと上手くつき合うことは、人生における重要なスキルの一つです。」
②「クライ・イット・アウト法を推奨する人は、すべての親がこの方法を使うべきであるとは言っていません。むしろ、子どもの睡眠問題に悩む多くの家族にとって、有用かつ安全な選択肢の一つになりうると主張しています。」「赤ちゃんが独りで眠れるようになり、自分を落ち着かせるスキルを身に着けることこそが、小児の睡眠障害を防ぐ最善の方法です。」
クライ・イット・アウト法を採用することが「良い」か「悪い」か、白黒どちらかの単純な結論に終わるものではなく、起きているときの安心・安全・幸福な昼間の生活の後でも、順調に寝入ることはできずにぐずったりするということはありがちなので、おむつ・病気などを確かめた後は多少はそのまま泣かせておくくらいは罪なことではないのでしょうね。