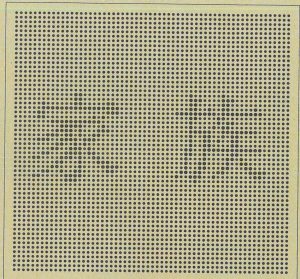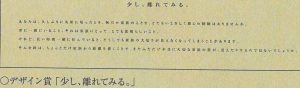日本では「イヤイヤ期」と言われるように、アメリカでも2才前後には、「何でも「イヤ!」と言う」「壁に絵を描く」「化粧品のクリームを塗りつける」「大泣きする」など、常識をはるかに飛び越える行動時期がある、ということが多かれ少なかれ観察され、いくつかの多く売れた育児書やドキュメンタリーから「魔の2歳児」の時期がほとんどの赤ちゃんにある、という考え・意識が広まったようです。(前掲書152ページ)
しかし、アメリカや・ノルウェーなどの広い調査研究書からは、「2歳児は1、3、4歳児と比べてもより魔であるとは言えないと考えられます。どんな行為をしでかすかは、個々の子どもによって千差万別ですし、どのように突飛な行為が収まっていくかの時期も、個人で様々です。」(同書155~156ページ)
日本での同様の印象を与える出来事としては、最初に書いたように「イヤイヤ期」と言われる現象でしょう。これについては、日本でも最近よく聞くようになった言葉ですし、子どもの自立への第一歩・「子どもの一つの成長の現象」として上向き・積極的・好意的に受け止め、一つ一つに子どもの意思をいったん受け止め、丁寧・冷静に対応していくことが大切でしょう。(東京都立大学教育学教授・酒井厚氏・ネット記事から)
対応法のコツの要点を述べてみます。
子どもの1~3才の時期は、行動も言葉も、日々目覚ましく成長・発達する時期です。毎日新しいことばを(一つ一つですが)幼稚園などで覚えてきてしゃべりますし、行動も毎日変わっていきます。そこをちゃんと見極め成長のたくましさ・力強さとして実感することが、子育てに立ち会う一番の喜び・感動であると思いますので、保護者の皆さんも、自分の思った通りにならずに叱ったり、もっともっといろいろとやらせたい、などと焦らずに、おおらかに見守ってあげてほしいと思います。子どもたちも、大人のしゃべること・やることをいつもいつも注意深く観察し、自分もあんな風にやってみたい・しゃべってみたい、と願いチャレンジしていますが、そう願ったとしても、すぐにできるわけでもなく、何度も失敗・言い間違いを繰り返しながらひとつひとつ習得していくものですから、じっくり・ゆっくり・焦らずにつき合ってあげていただきたいと思います。
私も、男の子一人と女の子一人を恵まれ、できる限りつきあいました。子が泣いている原因がわからずに悲しく思った経験は少なからずありますが、「イヤイヤ期」を経験しているなあ、と思ったことは皆無です。酒井厚氏の調査によると、4分の1の子どもの保護者はそういった回答をしています。
気になるその背景としては、次の5点ほどと考えられます。
①うちの家族には、祖母(私の母)がまだ元気でいて、親子の理解者・協力者としていてくれたことです。何人子どもを育てても、子育てには疑問・迷いが絶えないものですし、そんなときには何でも愚痴のように話すことで、悩みは解消しますし、親(私たち夫婦)のストレス解消になりました。
②家庭の状況として、大きな変動はなく、親子・家庭の情緒が安定していました。
③近所・寺の門徒さん・親戚・知人友人など、多くの人々に愛され声かけされ、温かく見守られる環境に恵まれていました。
④下の子が生まれたときは、上の子は小学2年生でしたから、「兄妹げんか」「上の子の赤ちゃん返り」などは、一切ありませんでした。
⑤以上のようないろいろな知見・知識・勉強を、子育ての前にしていたことを参考にできました。
今後は、こうした知識を、皆さんがあくまで参考にしながら、試行錯誤しながらご自身の子育てに生かしていかれることをおすすめします。