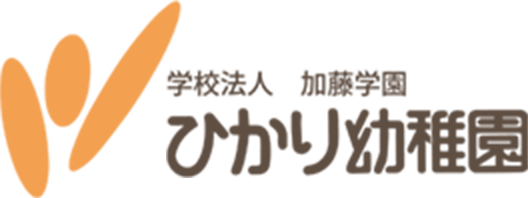本欄前回まで3回ほど、汐見稔幸氏『ほめない子育て』によって、子どもへのどんな声掛けが望ましいかを考えてきましたが、私の本棚に上記の本がありふっとタイトルが目に留まったので、あらためて読んでみました。これまで子どもの知力・学ぶ意欲・ことば育てについて2年ほど前にも20回ほど続けていろいろな知見を紹介しましたが、今回の本も、著者ならではの見解・具体例も述べられていますので、ご紹介しながら子育てについて考えてみましょう。
この本は1989年(平成元年)出版なので、主に昭和後期の教育事情を踏まえていますが、令和の現代もかなり共通の問題・子育て親の悩みもあると思います。
宇佐美覚了氏は、まず現代の子育て・教育の諸問題として、不登校・三無主義(無気力・無関心・無感動)・校内暴力・家庭内暴力・非行・自殺などが頻繁に報道される中でそれらを深く憂慮(ゆうりょ)され、教育現場でも多く保護者からの相談に乗って考える中で、これらの問題の多くは、学校教育におとらず家庭の教育をちょっとあらためるだけでかなり減少するのではないか、と提言されています。
以前にもいろいろな視点から家庭教育の課題・問題の原因を考えてきましたが、やはりいくつかの柱に整理できるようです。
- 過干渉・管理・支配
- 過度の心配性
- 過保護(甘やかし):子どもが自分でなんとかできることも、保護者が先取りしてやってしまう
- 過服従(子の言いなりになる)
- 過度の期待
- 無関心・無視・拒否・完全放任(育児放棄)・愛情飢餓
これらの言葉は、たいへん極端に聞こえますが、保護者が何気なく言った言葉でも、子どもは傷つくこともあり、冷静に反省する必要があります。
子どもも成長途上の独立した一人格であり、人権を尊重されなければならない存在であります。次回には、具体的にどんな状況で、どんな言葉がけをすればいいか?という問題について考えていきましょう。