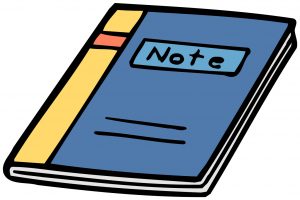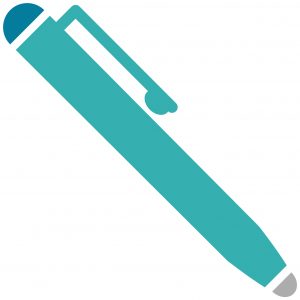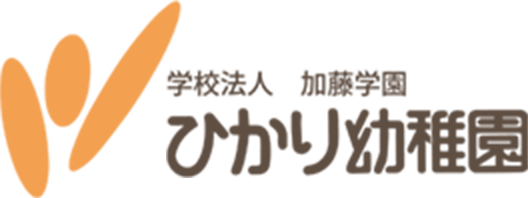少し長いですが、以下の文章を読んでみてください。
次のような報道を例に、具体的に考えてみよう。
「サッカーの人気チームで監督(かんとく)が辞任することになり、Aさんが新しい監督になるのではないかと注目が集まっている。」
ここで、まず大切なのは、結論を急がないことだ。すぐに「新監督はAさんか。」と決めつけてはいけない。世の中の出来事には、さまざまな見方がある。新しい情報を聞けば聞くほど、だんだんと多くのことが見えてきて、少しずつ事実の形が分かっていく。まずは一度落ち着いて、『まだ分からないよね。』と考える習慣をつけよう。
そして、いったん立ち止まったら、次は、メディアが伝えた情報について、冷静に見直してみよう。
この報道の中で、「Aさんは、報道陣をさけるためか、裏口からにげるように出ていきました。」というレポートがあったとする。これを聞くと、あなたは、Aさんが何かをかくしているように思わないだろうか。しかし、裏口から出たのは、その方向に行く必要があったからかもしれない。こう想像してみると、「報道陣をさけるためか」というのは、レポーターがいだいた印象にすぎない可能性がある。また、急がなければならない理由があったかもしれないから、「にげるように」も印象だろう。このように、想像力を働かせながら、一つ一つの言葉について、『事実かな、印象かな。』と考えてみることが大切である。このレポートから、印象が混じっている可能性のある表現を取りのぞくと、結局、確かな事実として残るのは、「Aさんは/裏口から/出ていきました」という言葉だけになる。ここには、Aさんが次の監督になると判断する材料は何もない。
いかがでしょう? 大人が読んでも、じっくり考えながら読まないと、真意・本意を正確に理解することは難しい論説文ですよね。
実は、この文章は、現在小学校5年生が使用している国語の教科書に載っていて、学校で先生の指導を受けて勉強している、情報に関する文章なのです。授業の後、テストにも出題され、この文章が主張する最終的結論を述べさせる問題も出ています。
私たちは日常生活で、TV・新聞・ネットなどで情報・報道を得ていますが、BGMや空気のように聞き流し、「ふ~~~ん・・・」と何気なく受け入れてしまうことが多いでしょうが、時には「ちょっと待てよ。」と立ち止まり、ああも考えられる、こうとも言える、などとあれこれ吟味しなおす必要もある情報も少なくないのではないでしょうか。見えていない面・書かれていない事柄(ことがら)・偏(かたよ)った感情に影響されている言説はないか? と自分なりにじっくり考えて、周りの意見・雰囲気に流されないように心がけるべき時もしばしばあるのではないでしょうか?