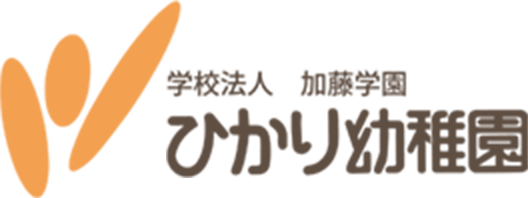IT機器・AIなど、デジタル機器の話が続きましたが、関係の深い最近の話題で、「チャットGPT」があります。これは、外国語からの翻訳・外国語への翻訳・長文の要約・悩みごとの相談(カウンセリング)・課題を与えると即座に一般常識をふまえ、多様な視点・角度を配慮した解答を即座に出してくれる、といった知的な作業を人間の代わりにやってくれる、という機器です。良し悪しにかかわらずどんどん進化しつつありますから、これも末恐ろしい感じがしますね。
私は、公的な文章を書いたり、役職・立場上の大勢の方々の前でのあいさつなどを課せられることが多いですが、学生時代から、指導教官に「自分の目でモノを見、自分の肌でモノに触り、自分の頭で考え、自分の言葉で文章を書きなさい! 人まねではまったく意味がないぞ!」と徹底的に指導されたたきこまれたこともあり、機械・機器にたよって文章・作品を創作することは、あまり興味が持てません。ですから当然「チャットGPT」などに触れたこともありませんので、それについてもっともらしく語る資格がないかもしれません。なので、他の学識経験者のことばを参考として紹介し、皆さんそれぞれの考えを深めていただくこととします。
解剖学者の養老孟司(ようろうたけし)氏は、「何か意味のあることを言ってきたとしても、機械が言ってると思うと白ける。僕は、解剖とか虫とかやっているから、後ろ側に実物がないとダメなんです。チャットGPTって後ろにはデータしかなくて、それを処理しているだけでしょう。ボールを投げたこともないくせに、ボールの投げ方をもっともらしく言う奴と同じです。」「AIはすでにある情報を処理することが得意で、その面での能力は人間をとっくに超えているから、そういうことはAIにまかせて、自分の身体を使って価値を生みだすことなど、AIにはできないことを発見していく生き方も見直されていくでしょう。」(『なるようになる~僕はこんなふうに生きてきた~』養老孟司著2023中央公論新社)
以前の本欄で、子どもの知的能力を育むために大切なことは、幼少のころから生の自然にふんだんに触れさせることだ、という最先端の科学者たちのことばを紹介してきましたが、養老先生も本質的には同じことを主張されていると思います。88才になられた養老先生は、今でも研究仲間から譲られた何千という昆虫の標本を作ることに没頭されているそうですよ。