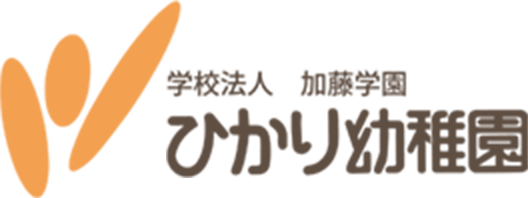今回は、成人・子どもに共通する一般的な健康の基本的な問題を幅広く考えてみたいと思います。子どもの教育・保育の問題からは、視点が少し変わりますが、私たち成人の健康の問題は皆さん誰しも少なからず関心がある問題だと思いますし、何より大人・保護者・保育者が健康で心身ともにゆとりをもってのびのびと教育・保育にあたっていかなければ、健全な教育・保育になっていかないと思いますので、必要・大切な課題だと思います。
日本の歴史上の医者や専門家の中でも、とても分かりやすく唱えられた健康法に、江戸時代の横井也有(よこいやゆう)(西暦1702-1782)という尾張の俳人の『健康十訓』があります。まずは列記してみましょう。
一.少肉多菜(肉を控えて野菜を多く摂りましょう。)
二.少塩多酢(塩分を控えて酢を多く摂りましょう。)
三.少糖多果(砂糖を控えて果物を多く摂りましょう。)
四.少食多噛(満腹になるまで食べずよく噛んで食べましょう。)
五.少衣多浴(厚着を控えて日光浴し風呂に入りましょう。)
六.少車多走(多歩)(車ばかり乗らず自分の脚で歩きましょう。)
七.少憂(少煩)多眠(くよくよせずたくさん眠りましょう。)
八.少憤(少怒)多笑(いらいら怒らず朗らかに笑いましょう。)
九.少言多行(文句ばかり言わずにまずは実行しましょう。)
十.少欲多施(自身の欲望を控え周りの人々に尽くしましょう。)
この前半の一.から六.は、健康のなかでも身体的な要素(食事をはじめとする生活様式)を、後半七.から十.は精神的な要素(気持ちの持ちよう)を謳(うた)っているようです。
肥満・高血圧・高脂血症・高血糖(まさに現代でいう“メタボ”)、更にストレス・がん・痛風など、今まさに注目されている生活習慣の問題点を、既にこの時代に示していることには驚かされます。
10項目すべてとなると難しいことですが、一つでもより多く心掛けたいものです。
また他に有名な例は、福岡藩の儒学者・貝原益軒(かいばらえきけん)が正徳2年(1712年)に描いたとされる『養生訓』(ようじょうくん)も、ほぼ同様の内容を盛り込んでいます。
次回は、横井也有の10ヶ条について、現代の話題にそって解釈してみましょう。